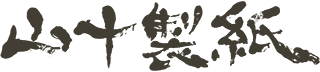美しい西島手漉き和紙の「にじみ」②
美しい西島手漉き和紙の「にじみ」 ②
西島手漉き和紙「画仙紙」の始まりの話です。
昭和20年頃西島では書道用半紙と養蚕に使う紙張(しちょう)が作られていました。

半紙は三椏の紙で薄く丈夫でにじみが少なく小さい文字を書くのに適した紙でした。
西島には紙を漉く「紙屋」と販売する「問屋」とがありました。その問屋の「たんば屋」現在の丹頂紙業の先々代の一ノ瀬憲氏が、東京神田の「清雅堂」でたまたま毎日系の書家、竹田悦堂氏と出会ったところから始まりました。
生前一ノ瀬憲氏から聞いた話ですと、画仙紙を求めに神田 清雅堂に来ていた竹田先生から「中国の四尺単宣がなかなか手に入らない」ことをお聞きし、西島で 四尺単宣を作ったら将来性があると知りました。
当時 四尺単宣 は中々流通が少なく戦後の書道ブームの始まりかけていた時期でした。
一ノ瀬氏は武田先生から詳しい情報を頂き、「中国では数年かけて材料を作ること、原料は藁とチンタンピという靭皮繊維を使うこと、美しいにじみがでること」を聞きました。
西島に帰り、当時30軒近くあった紙屋の中から、一番研究熱心なカネキ製紙の佐野清亀氏に研究をお願いすることになりました。
当時西島では三椏の書道半紙を作っていました。ミツマタの繊維は長さと太さがそろっていて、あまりに規則正しく揃っているので紙を漉き重ねて絞ったあと一枚づつ紙床(しと)から剥がすときに下の紙がまとわりつき薄く剥がれてうまく剥がれません。これを西島では「ねずる」といって紙干し作業の大敵でした。
そこに藁の繊維を加えることで、3mm程度の藁と1mm以下の藁がまざり紙を漉くときに、最初に簾に接している面は簾の隙間から細かい藁の繊維が落ち三椏の長い繊維がのこり、その三椏の繊維がフィルターになり三椏と藁の繊維が乗っていきます。
ですから、一枚の紙の断面を考えると、一番下に三椏の繊維がありその下に藁と三椏の繊維の層ができ、一枚の紙を構成しています。
これを漉き重ねていって、絞り、一枚づつ使途から剥ぐときには完全な層になって上下の紙に区別が出来上がっているので剥がしやすくなっています。
そこで使う稲わらを処理する技術は持っていました。あとは稲わらと三椏から樹脂を取り除ければよいことになります。
佐野清亀氏は一ノ瀬氏の依頼通りに何度も、何度も、何種類もの原料を試し、煮塾の具合を変え、配合を変え沢山のサンプルを作ったそうです。
出来上がったサンプルを持ち上京して清雅堂で悦堂先生に渡して結果を聞いてまたサンプルを作る。これを何度か繰り返すうちに竹田先生も山梨に足を運ぶようになりました。そのころには一ノ瀬氏は他の紙屋にも呼びかけ佐野氏と協力して画仙紙を作る研究会をつくりました。
数年後、一度使った三椏の紙と稲わらを配合し中国の四尺単宣に匹敵するようなにじみを生み出す「甲州画仙紙」を生み出しました。
たちまち20軒あまりの紙屋が出来上がったばかりの画仙紙の生産に乗り出しました。
年に数回は竹田先生を西島に招いて各工場の画仙紙を持ち寄りにじみの評価を頂き、みんなで意見を出し合って、昭和30年頃からは東京の画仙紙のほとんどが西嶋和紙になるまでに成りました。
戦後の混乱の中、村を挙げて「にじみ」に取り組んだ先代、先々代の紙屋が作り上げた西島手漉き和紙の大きな財産です。
偶然の出会いをきっかけに村を興した大きな産業になった、某テレビ番組の足袋屋のような話が西島にあったという事です。